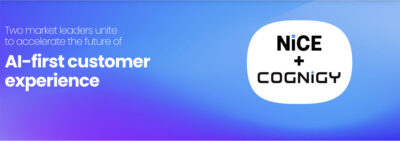静かに進む気候崩壊:欧州の異常気象とその影響〜生活者としての観点から
日本の夏も年々気温が上昇し、非常に過ごしづらくなってきています。ドイツや欧州でも洪水や森林火災が多発し、その被害は深刻さを増しています。世界的に見ても、気候変動の影響による「異常気象」は、もはや特別なできことではなくなりつつあります。今月と来月はそんな気候変動について考えてみたいと思います。今回は、現在の欧州での生活について取り上げます。
静かに進行する「異常気象」の常態化
今年の夏も、南欧を中心に過去の記録を超える猛暑日が観測されました。ドイツの首都・ベルリンでも、夏は比較的乾燥していて気温もそれほど上がらないのがこれまでの常でしたが、最高気温が37度まで上がった日がありました。ドイツの住宅では、日本のような空調設備が整っておらず、暑さ対策が間に合っていないのが現状です。気温が高い日は、法令で学校が短縮授業となってしまいますが、このような温暖化が続くと、従来の基準のままでは、もはや授業が成立しないといった状況にもなりかねません。
また、2024年にはドイツ南部のバイエルン州やバーデン=ヴュルテンベルク州が洪水に見舞われました。長引く豪雨により河川の水位が急上昇し、広範囲にわたって浸水。ドイツ軍やバイエルン赤十字を含む多くの救援措置が必要となりました。
一方で、森林火災も深刻化しています。発生件数や被害面積の推移は、いくつかの要因に左右されますが、火災の最も一般的な原因は「過失」と言われます。ただ、2018年や2019年のような極端に乾燥した夏が頻発し、火災リスクの高い日が増えることが懸念されています。気候変動の結果によって森林が燃えやすい期間が長くなるのであれば、森林火災の件数は今後さらに増加することが予想されます。
こうした状況はドイツに限った話ではなく、ギリシャ、イタリア、フランス南部など、南欧を中心により深刻化しています。
「異常気象」がもはや特別な現象ではなくなってきている――これが、今の私たちが直面する現実なのです。

欧州の気候変動が日常生活にもたらす影響とは
ドイツの森と火災リスクは、乾燥と管理不足の影響が大きいとされていますが、火災によって森林が失われれば、CO₂吸収源としての役割も同時に失われます。そのため、フランスやスペインなどを見舞う熱波や干ばつは農作物への被害だけでなく、水不足も引き起こしています。最近、オリーブオイルの価格が高騰していますが、それも気候変動と無関係ではないかもしれません。
また、農産物への影響はヨーロッパ域内にとどまりません。気候変動は地球全体の問題であるため、生産者であるアフリカや中南米も無縁ではありません。昨年はオレンジの収穫量が減少したことでオレンジジュースの極端な価格上昇が発生し、今年はコーヒーやチョコレートの価格上昇が見られます。
生活インフラへの影響も深刻です。都市部では集中豪雨、いわゆる「ゲリラ豪雨」によって、わずか数時間で生活インフラが麻痺するリスクも高まっています。台風のような突風に突然見舞われるということも少なくありません。日本のような自然災害への耐性がヨーロッパは少ないため、ベルリンでも、近年は悪天候によって市内の交通網が機能不全に陥ることが増えてきたと実感しています。日本から出張されているみなさんは、先日お伝えした長中距離合わせてのストライキの多発とも合わせて、移動手段に事欠く場面に遭遇することも多いのではないでしょうか。

私たち個人は何ができるのか
気候変動は個人の努力だけでは止められませんが、「関心を持ち続けること」や「生活の中の選択を見直すこと」には大きな意味があります。たとえば、エネルギーの使い方や食の選び方、投票行動や署名活動を通じて声を届けることもそのひとつです。
森林火災の「過失」を防ぐ教育キャンペーンなどの対策もその一つに挙げられるでしょう。ただ今年のドイツの選挙結果を鑑みると、昨今の経済状況の悪化や防衛への危機感から、環境や気候変動への関心が薄くなっていることも懸念されます。また、口では気候変動の重要性を唱えていても、実際の行動が伴っていないこと(ゴミ分別への無理解やEコマースへの依存等)がドイツでは多々見られます。
子どもたちが通う学校が暑さで頻繁に短縮授業になる。豪雨で交通機関が麻痺する――そんな日常の小さな異変から、世界がどう変わってきているのかを見つめ直すこと。そして「遠い国の問題」「未来の問題」ではなく、いま、ここで生きる私たちの問題として捉え直すこと。自分たち一人一人がどのような行動を取ることができるのかを考えること。それが、気候変動という見えづらい危機に対してできる、最も基本的で力強い一歩なのかもしれません。
ただ気候変動への取り組みは個人よりも国や企業の努力がより必要であると考えます。来月はドイツを例に、気候変動にどのような取り組みが行われているのかを取り上げます。
出典・参照
DLR. Hochwasserkarten und Lageinformationen für Süddeutschland.
Umwelt Bundesamt. Waldbrände.
希代 真理子(きたい・まりこ)
メディア・コーディネーター
1995年よりドイツ・ベルリン在住。フンボルト大学でロシア語学科を専攻した後、モスクワの医療クリニックでインターン。その後、ベルリンの映像制作会社に就職し、コーディネーターとして主に日本のテレビ番組の制作にかかわる。2014年よりフリーランスとして活動。メディアプロダクションに従事。2020年にAha!Comicsのメンバーとして、ドイツの現地小学校を対象に算数の学習コミックを制作。2023年3月に初の共著書『ベルリンを知るための52章』刊行(明石書店)。