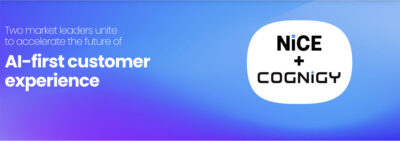「フィンランド化」の終焉とNATO加盟 ~歴史的文脈から見るフィンランドの現在と展望~
はじめに
「フィンランド化(Finlandization)」。
誰もが一度は耳にしたことがあるだろうこの言葉は、東西冷戦期において、ソビエト連邦という強大な隣国と協調・共存せざるを得なかった小国フィンランドの特異な外交姿勢を語るものとして広く知られてきた。
フィンランドは第二次世界大戦の終結後、独立国家としての存在を維持しながらも、強国ソ連の機嫌を損ねないよう念には念を入れた外交・安全保障政策を選択、採用し、半ばその見返りとして独立国家としての主権や民主主義体制を堅持してきたと言える。
フィンランドのこうした外交・安全保障政策は、小国外交の成功例の一つとして賞賛されることが多かったが、同時に「自主的な従属」以外の何ものでもないといった批判的論評も少なくなかった。
しかし2023年、フィンランドは北大西洋条約機構(NATO)に正式加盟し、戦後80年にわたり貫いてきた外交・安全保障政策の一大変革に踏み切った。「フィンランド化」の自主的放棄と歴史的終焉である。
本稿では、戦後80年に及んだフィンランド独自の中立外交の歴史を振り返りながら、NATO加盟の背景と今後の展望について概観したいと思う。

東西冷戦期における「フィンランド化」
日本人にはあまり知られていないかもしれないが、フィンランドとソ連は、1939年から1944年の5年間に2度戦火を交えている。「冬戦争(1939年〜1940年)」、「継続戦争(1941年〜1944年)」と呼ばれるものである。
この2つの戦争の結果、フィンランドは敗北し、国土の約10%(約44,000平方キロメートル)をソ連に割譲した。全長1,340キロメートルに及ぶ国境線はこのとき定められたものである。

1944年、両国の間で休戦協定が締結され、フィンランドは第二次世界大戦の当事国から離脱した。そして1948年、「フィンランド=ソ連友好協力相互援助条約(YYA条約)」が締結されて以降、フィンランドはソ連の軍事的影響を受けることを前提とした中立政策を展開していくこととなる。
これは事実上、北大西洋条約機構(NATO)をはじめとする西側の軍事同盟から一定の距離を置くことを意味した。フィンランドは中立国として、東西冷戦下のヨーロッパにあって独自の路線を築いていった。
「ソ連の軍事的影響を受けることを前提とした」中立政策は、外見上はたしかに「中立」なのだが、その内実たるや外交や報道、教育分野等においてソ連に対する配慮が強く求められるという側面を含んでいた。民主主義の根幹とされる言論の自由に関して言えば、自己検閲が常態化し、ソ連に対する批判的言動は慎重に取り扱われた。西側諸国が「フィンランド化」と呼称したのは、同国のこのような国内事情を憂慮、あるいは揶揄してのことである。
冷戦終結後の転換、EU加盟
1991年、ソビエト連邦が瓦解したことにともない、フィンランドはようやく「中立国」としての立場を再定義する好機を得た。
1995年には欧州連合(EU)に加盟し、西側陣営への統合を進めた。しかし、軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)への加盟は控え、従来の「非同盟」姿勢を追求した。
これは隣国ロシアとの地政学的関係に配慮した戦略であるとされるが、国内世論もまたNATOへの加盟を支持しなかった。
ウクライナ戦争の勃発と国内世論の激変
フィンランドにとって今世紀最大の転機となったのは、2022年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻である。ヨーロッパ各国を震撼させたこの大事変は、フィンランドの人々が長く信じ、支持してきた「中立による安全保障」への信頼を一気に切り崩した。
ウクライナ侵攻が起こるまではNATO加盟に反対、もしくは慎重だった国民の大多数が、一夜にして加盟支持へと傾き、政府・与党も迅速に反応した。侵攻からわずか3か月後の5月、フィンランド政府は正式にNATO加盟を申請し、翌2023年4月、加盟が承認された。フィンランドは80年もの歳月をかけて築き上げてきた非同盟政策を自ら放棄し、西側の集団安全保障体制の一員となったのである。
北大西洋条約機構(NATO)加盟に関する国民の支持率(2021年〜2023年)
| 2021年 | 約25% |
|---|---|
| 2022年2月(ウクライナ侵攻直後) | 約53% |
| 2022年4月 | 約72% |
| 2023年 | 約78% |
NATO加盟の意義と今後の課題
フィンランドのNATO加盟は、たんに軍事的防衛力を高めるのみならず、独立国家としての主権行使の強化、さらには隣国ロシアの影響力からの完全な自立をも意味する。歴史的に「大国とのバランス」に腐心してきたフィンランドにとって、これは国家存亡をかけた一大決心だったに違いない。
しかし一方で、NATO加盟以降、ロシアとの関係は悪化の一途をたどっている。事実、ロシア政府は「報復的措置」までも示唆している。今後、国境地帯の軍事的緊張やハイブリッド攻撃(サイバー攻撃や偽情報の流布など)が懸念されており、NATO加盟は「安全保障の強化」とともに「リスクの顕在化」をももたらしたと見るべきであろう。
おわりに
フィンランドのNATO加盟は、「フィンランド化」と呼ばれた東西冷戦期の外交テーゼに終止符が打たれたこと、さらには、ヨーロッパにおける国際政治の潮流が根底から変化してきていることを象徴的に示している。フィンランドはこれからNATOの一員としての「権利と義務」、「責任と期待」を背負いながら、いかにして自国の安全と独立を守り抜いていくかという新たな課題に直面している。
フィン人のルーツは中央アジアにあるとされる。これが事実ならば、フィンランドは私たち日本人と同じくアジアにルーツを持つ民族の国家ということになり、いっそう親近感が湧いてくる。日露戦争の間隙を縫って最初の独立を果たしたという歴史的事実もまた、こうした感情を後押しする。
新生フィンランドへの高い関心と期待を持ち、注視しつづけることは、ある意味で日本の責務でもあるのではないだろうか。少なくとも筆者は、そう考えている。
参考文献・資料
- Ministry for Foreign Affairs of Finland, Security and Defence Policy of Finland(2022年)
- Ministry for Foreign Affairs of Finland, Finland’s Foreign and Security Policy
- Finland’s Accession, NATO and Finland: Partners and Allies
- Atlantic Council, Finland’s Path to NATO Membership(2023年)
- The Economist, “The End of Finlandization”(2023年4月)
- “The Geopolitics of Finland: Neutrality to NATO”(Charly Salonius-Pasternak著 FIIA:フィンランド国際問題研究所)
- フィンランド国営放送(YLE)世論調査データ
- 『フィンランドの政治と外交』(北欧研究所、2021年)
副島 暁啓(そえじま・あきひろ)
株式会社ジェイシーズ 代表取締役CEO
海外事業展開・戦略コンサルタント&サポーター
MPS(政治学修士(英国)|国際政治・外交政策論)
大手光学機器メーカー、映像・精密機器メーカーにおいて、20年以上にわたり海外事業戦略、海外マーケティング領域に従事する。
この間、英国、ドイツ、米国、シンガポール、香港などに駐在または長期滞在し、事業戦略策定、販路開拓、エリア・マーケティング、組織再編・再構築、現地法人立ち上げ・マネジメント等に携わる。
2016年11月、それまで培ってきた見識やネットワークを基礎に、日本企業の海外事業展開をサポートするコンサルティング会社「株式会社ジェイシーズ」を設立した。
以来、60か国以上に展開する独自のアライアンス・ネットワーク、各国・各地域で活動する160人のメンバーとともに、海外ビジネスに勤しむ企業経営者、事業責任者と真正面から向き合う日々を送っている。
神戸大学にて国際関係論を、英国イーストアングリア大学にて国際政治・外交政策論を学ぶ。
「海外でビジネスをするなら、その国の歴史や文化、人々を尊ぶこころが大切だ」が持論。
座右の銘:Be the change you want to see in the world. (Mohandas Karamchand Gandhi)
大切にしているもの:1989年11月に崩壊した「ベルリンの壁」の断片