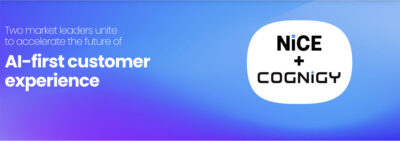ドイツ経済の現状:ドイツの景気は本当に良いのか?
昨年、日本が国内総生産(GDP)でドイツに抜かれ、世界4位に転落したというニュースが話題になりました。しかし、果たして数字上、日本よりも裕福だとみなされているドイツの景気は本当に良いと言えるのでしょうか。EU(欧州連合)の大黒柱として知られるドイツですが、成長鈍化や社会問題など、日本からでは見えにくい課題も抱えています。本日は、マクロ経済データや政策動向、筆者の肌感覚を交えて、現状を整理してみたいと思います。
マクロ経済の現状
まずは、公的統計をもとに主要なマクロ経済指標を確認してみましょう。
- 実質GDP成長率:2023年、2024年とドイツは2年連続マイナス成長です。2025年はプラスに転じるかと期待されていますが、決して大きな成長は見込めないと予想されています。長期的には成長鈍化傾向が続いており、かつての「欧州の輸出・製造立国」としての勢いは影を潜めつつあります。
- 失業率・雇用:ドイツの失業率は約3-4%で推移しており、他のEU諸国に比較したら水準としては低いものの、高度技能人材や特定産業の人手不足が顕著になっています。ドイツは学歴や職業訓練が雇用に直結するため、流動的な対応が難しいと言われています。
- インフレ:ロシアのウクライナ侵攻後、エネルギー価格高止まりの影響で消費者物価は上昇して、家計の購買力が圧迫されています。HICP(Harmonised Index of Consumer Prices : 統一消費者物価指数)では、2023年は前年比約6%増とかなりのインフレを記録しましたが、それ以後は前年比2%程度で推移しています。
- 賃金・所得統計:毎年最低賃金が上昇していることから名目賃金は上昇しているものの、インフレを考慮すると実質購買力の伸びは限定的と言えそうです。一般市民の生活コストはインフレで上昇傾向にあり、賃金の上昇が生活の豊かさにつながらないのが辛いところです。
このように、ドイツ経済は一見安定しているように見えるものの、成長鈍化や物価上昇など複数の課題を抱えています。
転換期を迎えるドイツ経済
さらにドイツ経済は、戦後長く続いてきた製造業中心の経済モデルからの転換期にあります。これまでドイツは、自動車・機械・化学といった高付加価値製造業を中心に、輸出主導型の成長を遂げてきました。しかし、エネルギー構造の変化や地政学的リスク、デジタル化の波が押し寄せるなかで、従来のモデルは大きな見直しを迫られています。
- 自動車産業:電動化やソフトウェア化への急速な移行が進んでいます。内燃機関中心の時代の強みが薄れる中、技術革新が競争力の鍵です。フォルクスワーゲン(VW)やBMW、メルセデス・ベンツなどの大手は、EV専用プラットフォーム開発に巨額の投資を行っていますが、米国のテスラや中国のBYDといった新興勢力との競争は激化しています。ドイツ国内では、部品サプライヤーを中心に再編やリストラが進み、雇用の不安定化も課題となっています。
この分野では、もはや「エンジン技術」だけではなく、「ソフトウェア開発力」と「データ解析能力」が競争の中心となりつつあり、産業構造全体の変革が求められています。
- グリーン技術・再生可能エネルギー:欧州全体の気候政策「Fit for 55」に沿った産業戦略を推進しています。これにより、再生可能エネルギー(風力・太陽光・水素)への投資が急拡大しています。
これは国際的な投資誘致や雇用確保にも影響する分野ですが、エネルギーコストの高さや送電インフラの遅れ、電力網整備のボトルネックが依然として成長の制約要因となっています。他のEU加盟国も同様で、EUやドイツの戦略自体が見直される可能性も否定できません。
- 国際競争力:米国のインフレ抑制法(IRA)対策のための米国への製造拠点移転は、EU・ドイツ内の産業空洞化を招く可能性があります。中国は依然としてドイツ製品の最大の輸出市場の一つでありながら、EV・バッテリー・太陽光パネルなどの分野で中国とドイツは強力な価格競争を行っています。
いずれもEUレベルでの産業・貿易政策の協調が不可欠であり、ドイツ単独では対応が難しく、加盟国間での大きな利害調整が発生することが見込まれます。

メルツ政権の政策
ドイツのメルツ政権は、こうした課題に対応するため、2026年の連邦予算案で大規模な投資計画を盛り込みました。総額5,205億ユーロの歳出のうち、過去最大規模となる1,267億ユーロを投資に充てる予定です。2026年連邦予算案は、単なる財政計画を超えて、ドイツ経済が直面する構造的転換を象徴しています。投資の重点分野は以下の通りです。
- 交通・エネルギー・デジタル化:老朽化した公共インフラの更新や再生可能エネルギーへの投資です。特に電力網や高速通信網の整備は、企業の競争力確保に直結します。
- 教育・医療・社会保障:学校や医療施設の改善、年金・介護制度の持続性確保をめざします。長期的な人口減少・高齢化対策の一環です。
- 防衛・国家的プロジェクト:憲法上の「債務ブレーキ」による新規借入制約を一部緩和します。財政規律を保ちつつも戦略的投資を可能にするものです。
※債務ブレーキとは、ドイツの財政規律を定めた憲法上の制度で、 国家財政の過度な赤字を防ぐためのルールです。連邦政府は、通常の歳出に対して構造的財政赤字を GDPの0.35%以下に抑える必要があり、地方自治体も原則として借入を行わない「均衡予算」が求められます。
予算案の議論は、単なる財政計画を超えて、ドイツ経済の方向性を示す「指針」となっています。積極的投資と財政規律のバランスが今後の成長を左右すると考えられ、成功の可否は今後数年間で明らかになるでしょう。
また、メルツ首相を中心とした首脳陣の連立政権の調整能力も大きな課題です。財政規律を重視する保守層と、投資や社会保障を重視する勢力との間で妥協点を見いだすことが不可欠です。なお、多くの投資が「連邦予算本体」ではなく、特別基金を通じて行われる可能性があります。特別基金の使い方や透明性が政策議論上の焦点になっています。
成長戦略、財政規律、社会的安定のバランスをいかに実現するかは、政策当局だけでなく企業にとっても重大な意味を持ちます。とりわけエネルギー・デジタル・人材といった分野への投資は競争力維持に直結し、今後の企業戦略や投資判断に影響を与えるでしょう。各企業はドイツの政策動向を注視し、自社のサプライチェーンや投資ポートフォリオを見直す局面に差しかかっているといえます。

生活者から見た社会的・政治的状況
経済指標や政策からだけでは見えにくいのが、家計や社会の実感です。筆者がベルリンで生活して感じるのは、街の雰囲気が以前よりやや緊張してきていることです。生活費や住宅費の上昇、インフレ圧力は市民生活に影響を与え、かつての寛容で落ち着いた雰囲気が変わりつつあります。一方で失業して仕事を探している人もよく見かけるようになりました。学歴と職歴のほぼ完全一致を求めるお国柄のため、人手不足を安易に埋められない状況で、チグハグさを感じざるをえません。
また、国が投資を渋ったツケが回ってきていることを日々実感しています。正確に動くことを期待すること自体が難しい鉄道や、修理に何ヶ月も有する公共エレベーターなど投資の停滞を目の当たりにすることも増えています。市民もそのような状況に対して、諦めの域に達しているように見受けられます。
さらに、先日初来日したドイツ人は「日本の方が裕福に見える」と語りました。長年ドイツで生活した日本人が本帰国して、「収入はドイツにいた時よりも減っているが、生活は豊かになった」という声も聞きました。為替や購買力を考慮すると、日本の方が生活水準は高いと感じても驚きではありません。米ドルベースの経済規模のランキングだけで判断するのは危険で、生活実感や消費動向も考慮すべきでしょう。
まとめ
ドイツ経済は表面的には安定しているように見えますが、成長鈍化、投資停滞、国際競争の圧力など、複数の構造的課題を抱えています。ドイツは決して「景気が絶好調」とは言えず、むしろ複雑な課題を抱えながら慎重に舵を取っている段階にあるのではないでしょうか。今後の政策と企業の対応に加えて、世界情勢などの変数に左右されるため、歯切れが悪いですが、成長の行方はプラスにもマイナスにも大きく変わると考えています。
繰り返しになりますが、ドイツだけではなく、日本との比較では、GDPの順位だけでなく、生活実感や購買力、社会制度の持続性を含めた総合評価が必要です。ドイツ経済の現状を理解するには、統計データ、政策動向、そして現地での実感を併せてご判断いただければと思います。
出典・参照
Bundesregierung aktuell. Newsletter 26.September 2025.
Deutscher Bundestag. Allgemeine Finanzdebatte zum Haushalt 2026.
European Central Bank. HICP – Overall index, Germany, Monthly.
European Commission. Economic forecast for Germany.
Reuters. What is included in Germany’s 2026 draft budget.
LBBW (Landesbank Baden-Württemberg). BIP Deutschland – aktuelle Daten und Prognosen.The World Bank. GDP growth (annual %) – Germany | Data.
ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung). Wirtschaftswachstum in weiter Ferne.
浜田真梨子(はまだ・まりこ)
執行役員
シニアマーケティングコンサルタント(欧州統括)
大手電機メーカーにて約10年に渡り、IT営業およびグローバルビジネスをテーマとする教育企画に従事した。その後コンサルタントとして独立し、日系・外資問わず民間企業や公的機関へのコンサルティングを行っている。中でもハンズオンベースでの調査から受注までの一連のプロセスをカバーする営業・マーケティング支援や、欧州拠点の設立などのサポートを得意とする。2016年には欧州で経営学修士号(MBA)を取得し、現在はドイツを拠点に活動している。