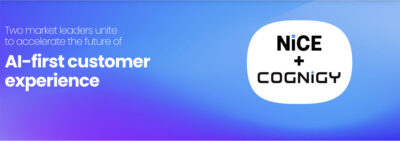ドイツの抱える社会問題とは〜第75回ベルリン国際映画祭の2本の映画から、移民と東西格差を読み解く
今回の総選挙前に、ベルリンでは75回目のベルリン国際映画祭が開催されました。本映画祭は、時事問題に敏感なことでも知られています。今年はドイツをテーマにした映画を2本鑑賞する機会がありました。その内容を紹介しながら、ドイツが根本的に抱える問題や今後の課題について考えてみたいと思います。
総選挙の結果
前回の投稿でも触れたように、2025年2月23日に投開票が行われた総選挙では、最大野党のCDU/CSUが第一党となり、極右政党であるAfDが第二党に躍進しました。AfDのワイデル共同党首は「私たちは主流派の政党の地位を確保した」と、勝利宣言を行い、さらに「次の選挙では最強の勢力としてCDUを追い抜く。それが我々の目標だ」と、すでに4年後の選挙を視野に入れた発言をしています。
ドイツはナチス時代の反省から、これまでに欧州や世界に対して、補償問題をはじめ多大な努力を払ってきました。そうした長い反省のプロセスを経て、国際的にも信用される国になったはずです。しかし、今回の選挙結果は、ドイツ社会の根底にある不安や分断を浮き彫りにしました。そういったことが今回ご紹介する2本の映画からも垣間見ることができると思います。
ハーナウで起こった人種差別襲撃事件を扱った『ドイツ国民』
ドイツには歴史的に移民・難民を受け入れてきた土壌があります。しかし、社会が不安定になるたびに、移民・難民が標的とされてきました。
『ドイツ国民 (Das Deutsche Volk)』は、2020年2月19日にドイツ・ヘッセン州のハーナウという町で発生した人種差別襲撃事件を題材にしたドキュメンタリーです。監督は、遺族や生存者を4年にわたって追い、残された人々の視点から丁寧に事件を描いています。
犯人は「ドイツ人とは思えない」という理由で9人の若者を射殺しました。被害者は全員、移民背景をもつ「ドイツ人」でした。
映画では、事件当日の警察の対応をめぐり、遺族が何度も説明を求める場面が描かれます。しかし、彼らの質問に対する明確な回答はなかなか得られず、遺族は自ら事件解明に向けて動き始めます。また、事件を風化させないために毎年行われているデモに対し、市から規模の縮小を求められる場面もありました。

2015年以降、ドイツは国境をほぼ開放し、シリアやアフガニスタンを中心に大量の移民・難民を受け入れてきました。しかし、それに伴い、不法移民の流入やテロ事件の増加なども起こり、国民の間に不信感や反移民感情が広がるという負のスパイラルが生じています。「ドイツ国民」とは体誰をさすのか––移民背景をもつ人々が国民の4分の1を占めるといわれるドイツにとって、国の在り方が問われています。
旧東ドイツの片田舎で暮らす青少年たちを描いた『パンチング・ザ・ワールド』
ベルリンの壁が崩壊して30年以上経ちますが、東西格差については、今もなお深刻な問題です。
『パンチング・ザ・ワールド (Mit der Faust in die Welt schlagen – Punching the World)』という映画の舞台は、旧東ドイツのラウジッツという地域の田舎町です。かつては炭鉱業で栄えましたが、現在はインフラが十分に整備されておらず、子どもたちはバスで学校に通っています。
この町はポーランドとの国境に近いため、隣国から低賃金労働者が流入し、地元のドイツ人の離職率が高くなっています。映画では、アルコール依存症に苦しむ父親や職場で奮闘する母親の姿が描かれています。そんな環境で育つ子どもたちは、行き場のないフラストレーションを抱え、破壊行為やネオナチのグループへの接近という形でそれを解消するしかありません。
この映画は、未だに解消されない東西ドイツの格差と、それが生み出す社会問題を浮き彫りにしています。
東西ドイツ統一後の1991年以降、移民に対する暴力の発生は、ドイツ民主共和国(旧東ドイツ)の統合政策の失敗と密接に関連しています。性急な統一プロセスと、それに伴う社会・経済の混乱が要因です。東西統一により国境は開かれたものの、旧東ドイツでは移民の受け入れ経験が少なく、産業の中心だった褐炭産業の段階的廃止による経済的・社会的不安が広がりました。
移民や難民だけではなく、この地域に古くから住む少数民族ソルブ人(スラブ系民族の末裔)も、ネオナチをはじめとする右翼過激派の標的になりつつあるといいます。

なお、映画では、産業が衰退したことで荒廃した町の暗い雰囲気と、一面に広がる菜の花畑や湖といった自然が広がる美しい風景が対照的に描かれているのが印象的でした。
これからのドイツの課題とは
正直なところ、これらの映画を観た後は、今回の選挙結果にある程度納得がいきました。大量の移民・難民の受け入れと統合の問題。性急過ぎた東西統一がもたらした格差と分断。結局、これまでの政権はこうした課題に対し、説得力のある具体的な解決策を提示できませんでした。その結果、不安や不満を抱える国民の支持を失い、大敗することとなったのです。
このまま具体的な解決策が示されない状況が続けば、冒頭で触れたAfDが第一党の地位を獲得する日が来るかもしれません。もしそうなれば、ドイツが欧州連合(EU)の結束するための役割を果たすことはますます困難になるでしょう。今後のドイツの社会・政治動向に、引き続き注目したいと考えています。
出典・参照
朝日新聞. 移民問題・東西格差が拍車 ドイツの右傾化、マスク氏らも加勢
朝日新聞グローブ. 極右政党AfDが躍進したドイツ総選挙 移民政策や欧州の団結への影響、課題を読み解く
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Region im Wandel/Eine kurze Geschichte der Lausitz75. Internationale Filmfestspiele Berlin. „Das Deutsche Volk“
75. Internationale Filmfestspiele Berlin. „Mit der Faust in die Welt schlagen“
希代 真理子(きたい・まりこ)
メディア・コーディネーター
1995年よりドイツ・ベルリン在住。フンボルト大学でロシア語学科を専攻した後、モスクワの医療クリニックでインターン。その後、ベルリンの映像制作会社に就職し、コーディネーターとして主に日本のテレビ番組の制作にかかわる。2014年よりフリーランスとして活動。メディアプロダクションに従事。2020年にAha!Comicsのメンバーとして、ドイツの現地小学校を対象に算数の学習コミックを制作。2023年3月に初の共著書『ベルリンを知るための52章』刊行(明石書店)。